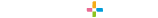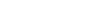日本らしく、夢の跡
試合終了の笛が鳴ると、選手が次々にピッチに崩れ落ち、西野監督もすぐに口を開くことができなかった。またもはね返された8強の壁。「三度目の正直」はならなかったが、今大会の日本は抜群の一体感で世界に立ち向かった。
チームを取り巻く狂騒の始まりは、成田空港にたった150人のファンが集まった見送りからだった。大方の予想は1次リーグ敗退。欧州での事前合宿で国内の関心の低さを指摘された西野監督は「初めて聞いた。盛り上がっていないんですか」と述べ、事情をのみ込めない様子だった。
世間の低評価をよそにチームは結束していた。大会2カ月前に緊急登板した西野監督と、ハリルホジッチ前監督時代に冷遇されながら、監督交代によって再び中心メンバーとなった本田ら。選手の顔ぶれは「年功序列」とやゆされたが、2002年日韓大会と10年南アフリカ大会で逃した決勝トーナメント初戦突破の目標を共有。その結び目は「日本らしさ」の追求だった。
南ア大会で本田、長谷部、長友、川島はW杯初出場を果たしたが、16強は結果ほどの甘美さはない。戦術は守備一辺倒。続く14年ブラジル大会は香川、吉田らを加え、史上最強と言われたが、攻撃重視の「自分たちのサッカー」は示せず、1次リーグで1勝もできずに敗退した。「日本化したフットボールで世界に衝撃を与えたい」との思いは、選手の胸にくすぶり続けた。
ハリルホジッチ前監督解任後の指揮を引き受けた西野監督も同じ理想を持っていた。主導権を握ってボール支配率を高め、日本人の機動力と技術力を生かしてゴールを攻略する。対話重視の考えも一致し、本田は「うまくマッチした」という。
日本代表の指揮はザッケローニ、アギーレ、ハリルホジッチと続いてきたが、今回のチームが目指したのは、外国人監督の押しつけではなく、日本人の、日本人による、日本人のためのサッカー。
川島は「やれることはやりきったという気持ち。ここにたどり着くまで一人一人が助け合ってきた。そいういうスピリットを見せられたのは誇り」と胸を張った。 (浅井俊典)