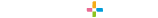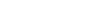7月15日
<ピッチの余韻 藤島大>監督選ぶ前に課題検証を
人気企業の採用担当者がいる。面接。過去に入社例のない大学の学生をなかなかよいと思った。さて採用と踏み切れるか。待てよ。社の一員になったものの、あまり仕事に向いていなかったら。きっと上層部に責任を問われる。やはり古くからたくさん採ってきた大学の卒業生が無難だ。仮に不向きでも「そういうやつもいる」で済まされる。
サッカー日本代表の監督選びに置き換える。
日本列島に生まれ育った者に代表の指揮を託し、もし足踏みをしたら、選ぶ側の逃げ場はなくなる。ここは名のある国の人間に。そういう心理がこれまでは働いた。
かくして2010年大会の岡田武史、今回の西野朗とベスト16進出を果たした両監督とも前任者の辞任と解任によって、あくまでも代役、後任として重責を担った。
さあ次は。森保一の名がしきりにささやかれている。広島を複数の優勝へ導いたのだから資格はある。
よく考える。サッカーとは別に「勝負」という競技があって、W杯のような場では、この一流でないと通じない。
元有名選手で負けてばかりのプロ監督よりも地域の普通の少年クラブを必ず強くするコーチに適性はある。負ける人は負けるし勝つ人は勝つ。
日本代表の監督は国籍を問わず「恵まれた選手層がなくても勝たせた人」に限る。
そして過去に目をつむれば未来はつかめない。西野体制のみならず、任を解かれたバヒド・ハリルホジッチ前監督の指導の実相、その長所を含めて、しつこい検証を始めなくてはならない。筋としては人選より先だ。 (スポーツライター)