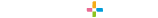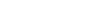7月2日
<ピッチの余韻 藤島大>心を解き放つ
土曜の夜、懐かしい友と会った。スポーツ好きの建築家だ。すぐに聞かれた。「あのサッカーのボール回し、どうなの」。ここは即答できる。
「間違いではない」
詳細は省くが、フェアプレーポイントなるものの存在を含め、あんな状況はまれである。そうであるから日本代表の西野朗監督もまれなる決断に踏み切った。
他者の結果にこちらの成否をみずから委ねる。なるほど普通ではない。しかし敗退の決まっているポーランドはしつこく球を奪いにはこない。確実に回せる。これはこれで判断材料だ。ざっと終了まで残り15分、コロンビアは守り切るだろうというのも合理からひどく外れてはいない。
ベルギー戦、どうなる?
「勝敗を明言はできない。ただ監督はあのことでカギを手にできた。選手の心を解き放つカギを」
たとえば決戦2日前、あるいは前日、日本の消極的選択を批判する海外の新聞のコピーを手にしながら、ミーティングでこう言葉を発する。
「オレだって記者ならこう書くさ。すべての批判はオレが引き受ける」
わっと叫ぶか、静かにつぶやくかは、その人の個性だ。そして続ける。
「ベルギー戦はここにいる一人ひとりのものだ。パッと心が求めたら従ってくれ。それができるから、それを許されるから、君は、君たちはここにいるのだ」
当然、相手を詳細に分析、対策を固めている。そうしないとピッチの秩序はない。限られた作戦の枠にあっても、個性は発揮される。よき監督はそのことを熟知している。 (スポーツライター)