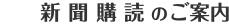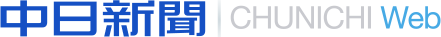全国
<安倍政策点検> 地方創生
2017年10月9日 紙面から
 |
「地方こそ、成長の主役」。安倍政権が掲げる看板政策「地方創生」は、東京への一極集中が進む人口を分散させ、地方の自治体に地域活性化の自助努力を促す狙いだ。2014年に始まった、この取り組みに成果はあったのか。取材した山村では、「何とかしたい」との思いを形にできない厳しい現実があった。
天竜川の谷あいに集落が点在する長野県最南端の天龍村。「客が減り、どの店も後継者がいない」と理容店を営む村商工会長の宮沢金治さん(75)は嘆く。村は六十五歳以上の高齢化率が全国で二番目に高い59%(一五年国勢調査)。昭和三十年代は六千人超の住民がいたが、今は千四百人足らず。人の姿はまばらだ。
商店の減少や住民の高齢化で買い物もままならない。そのため村は昨年、お年寄りにタブレット端末を貸し出し、インターネットを通じて食料品や日用品を注文できる配達サービスを計画した。着目したのが地方創生の交付金だった。
国からこの交付金を受けるには、民間と連携するなどの条件を満たす必要がある。村は地元商店と手を組もうとしたが、商店側は「経費を負担する余裕も、人手もない」。商店主もまた、多くが高齢者。国側との交渉の最中、計画自体が頓挫してしまった。
その後も村は交付金を活用しようと全職員からアイデアを募るが、一つも形にはなっていない。永嶺誠一村長(54)は「過疎が進んだ村で交付金の条件を満たすのは難しい。国に末端の窮状を知ってほしい」。
これまでも、過疎が進む現状に手をこまねいていたわけではない。二十年以上前から移住者への助成金、空き家購入補助などを実施。村名にちなんで「ドラゴン村の嫁さん探し」と名付け、都市部の未婚女性を招くお見合いイベントも開いた。だが、結婚などでわずかに増えても、都会への転出や死亡が上回り、人口減は止まらない。職員時代から対策の先頭に立ってきた永嶺村長は「人がいないと村は成り立たない。常に危機感がある」。
今年七月末にも周辺自治体と合同で、東京で移住希望者向けセミナーを開いた。村のブースに田舎暮らしを望む子連れの三十代の夫婦が訪れ、村へ下見にも来てくれた。
移住定住推進係の係長は「若くて理想的な家族。人口が三人も増える」と喜んだが、夫婦は結局、他の町への移住を決めた。「人口の争奪」は自治体間でも厳しさを増す。
地方の苦労をよそに、首都圏は人を吸い寄せる。
二〇二〇年の東京五輪に向け、急ピッチで建設が進む新国立競技場。工事現場には十台以上の巨大クレーンが林立し、つち音が絶えない。夕方、仮設の塀の扉から一人、また一人と作業員が帰途に就く。足場を設ける下請け業者の男性社員(25)は、伊豆半島の静岡県河津町から四年前に上京。「東京でしかできない仕事に魅力を感じた」と話す。
地元で働いていた時より給料はよく、五輪がある三年後には長女が小学校へ上がる。魅力的な都会生活に迷いを感じさせない口調で言う。「地元に戻るつもりは、ないですね」
安倍政権の地方創生の総合戦略は一三年に十万人の転入超過だった東京圏への人口移動を、二〇年に「均衡」させるとしている。だが、一六年の転入超過はむしろ十二万人に拡大。東京一極集中に、歯止めがかかる気配はない。
<地方創生> 国、自治体それぞれが総合戦略を定め、少子化対策や雇用創出などの2020年までの数値目標を設けた。定住促進や観光、産業振興などに取り組む自治体の先進的事業を国が審査し、総額1000億円(17年度)の交付金を配る。事前に使い道を決める必要があり、事業成果の検証も求められるため、申請に慎重な自治体は少なくない。
◆無理筋、政争の具に
<東京大法学部・金井利之教授(自治体行政学)の話> 自治体に実現不可能とも言える数値目標を掲げさせ、国が一方的判断で「優れた」提案を選び、財政支援する枠組みが、安倍政権の地方創生の正体だ。
自治体は、人口や交付金で限られた枠を奪い合う「共食い」を強いられている。国自らはアイデアを示さず、相撲の行司のように振る舞うだけ。自治体は土俵に上がらないことが、最良の選択だと考えている。
国の本来の役割は、どんな所に住む国民でも生活していける社会基盤を整えること。その土台があってこそ、自治体や民間の創意工夫は生きてくる。短期で成果が上がるはずもない地域活性化策を政争の具にした安倍政権の失策だ。人口減少社会における活性化の意味を問い直すべきだろう。


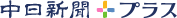


 データで見る「自民大勝の内訳」
データで見る「自民大勝の内訳」 小選挙区の開票(中部9県)
小選挙区の開票(中部9県) 比例ブロックの開票
比例ブロックの開票 党派別の獲得議席数
党派別の獲得議席数 最高裁裁判官 国民審査
最高裁裁判官 国民審査